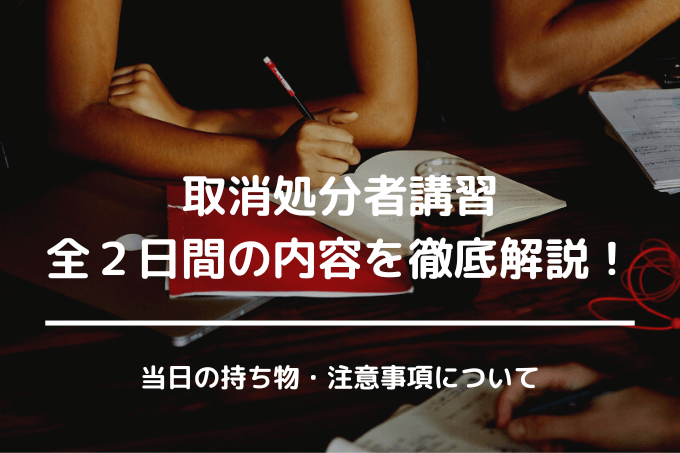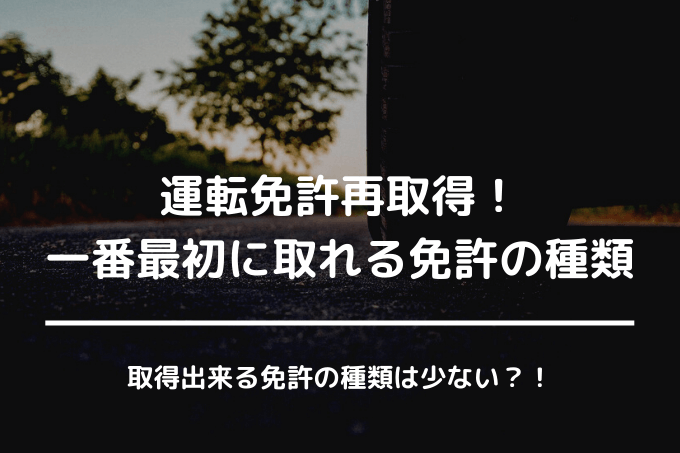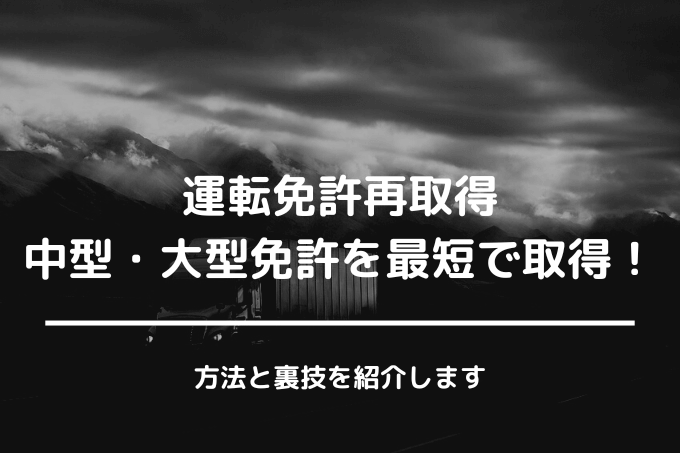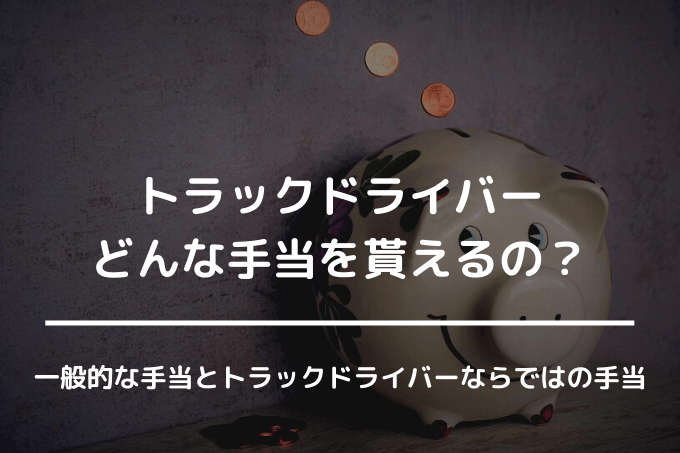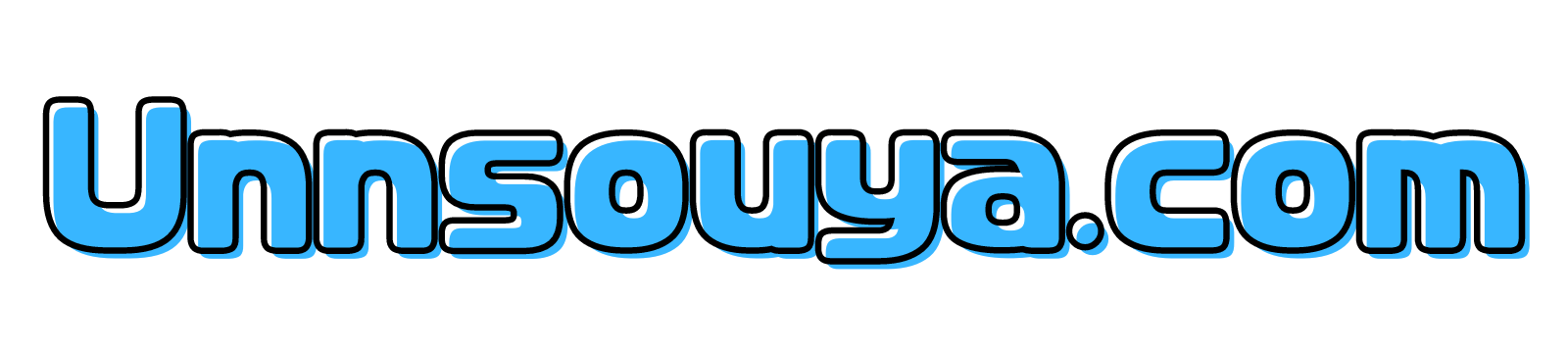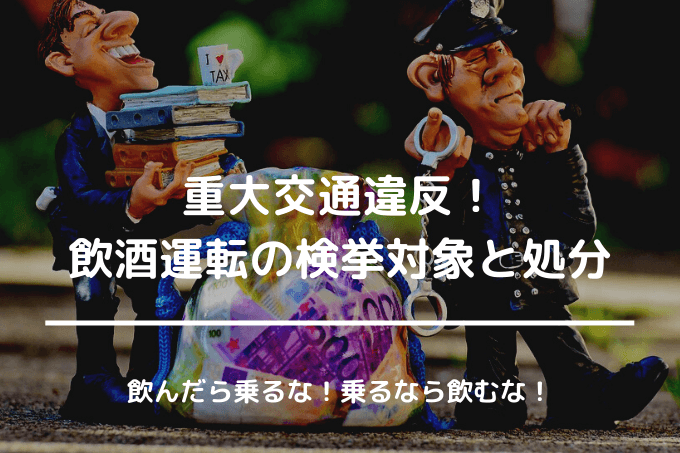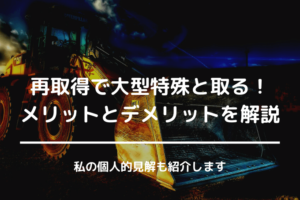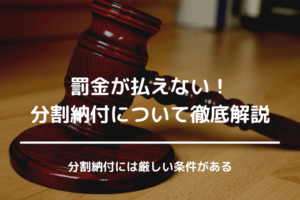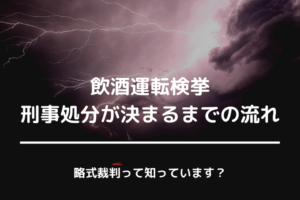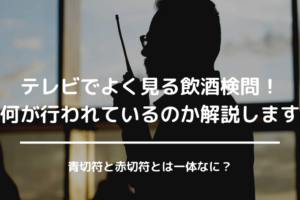はじめに

まずはじめにこちらをご覧ください。
- 飲酒運転とはそもそも何なのか
- 飲酒運転の取り締まり対象について
- 飲酒運転の処分について
どんなに悪質な飲酒運転の報道がされても、飲酒運転が原因の悲惨な事故報道がされても、飲酒運転をする人は後を絶ちません。
トラックドライバーがトラックを運転中に飲酒運転をして、死亡事故を起こすという、一般の人は元より、運送業界経験者からしても、『絶対に許すことが出来ない』極めて悪質な飲酒運転が多発しています。
今回は、飲酒運転がどれだけ悪質で、どれだけ愚かなことなのかを知っていただくための記事になります。
飲酒運転とは

当たり前の説明になってしまいますが、改めて飲酒運転とは、アルコールを飲酒後、そのアルコールの影響がある状況で自動車・バイクなどの車両を運転する犯罪行為のことを言います。(自転車を運転しても飲酒運転になります)
年々罰則が強化されていますが、いまだになくならない悪質な重大交通違反・重大犯罪です。
飲酒運転の取り締まり対象
呼気(吐き出す息のことを言います)1リットルあたりに含まれる、体内のアルコール濃度が0.15mg以上検出された場合。
何時間前に飲み終えていようが、飲酒検査で0.15mg以上アルコールが検出された場合は、全て飲酒運転での取り締まり対象になります。
1.基準値(0.15mg)以下の場合
上記で解説したように0.15mg以上が飲酒運転の取り締まり対象ということですので、それ以下の場合は取り締まり対象にはなりません。
もしも体内にアルコールが検出されても検挙されることもありませんし、処分を受けることもありません。
だからと言って良いわけではありません。
道路交通法第65条1項には、『何人(なんびと)も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない』と記載されています。つまり数値がどうであれ、酒気を帯びた状態での車両の運転は絶対にしてはいけないということです。
2.飲酒検査を拒否することは出来ません
体内のアルコールを調べる際に《飲酒検査》というものが行われます。
検査時の飲酒の有無に関わらず、警察官が行う飲酒検査を拒否すると、《飲酒検査拒否罪》という犯罪になり刑罰の対象になります。(3ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金)
したがって飲酒検査を拒否することは出来ません。
酒気帯び運転と酒酔い運転

0.15mg以上が検出され、取り締まりを受けた場合、飲酒運転は酔いの状態によって『酒気帯び運転』と『酒酔い運転』のどちらかに分けられます。
1.酒気帯び運転とは
すごく分かりやすい言い方をすると、酒気帯び運転とは取り締まり基準値0.15mg以上検出された人のことを指します。上限はありませんので、どんなに高い数値が検出されてもです。
2.酒酔い運転とは
酒酔い運転とは、その呼び方の通り、酒に酔った状態で車両を運転することです。
酒に酔った状態とは、壁や人などの支えがないと立っていることが出来なかったり、質問に受け答えが出来なかったり、ろれつが回らず正常に話すことが出来ないなど『アルコールの影響で正常な運転が出来ない恐れのある状態』を指します。
この酒酔い運転は、検出されたアルコール濃度の数値は問いません。(検出されたアルコール濃度が0.15mgであっても、0.50mgでもです)
3.酒気帯び運転<酒酔い運転
検挙された際の罪は、酒気帯び運転より酒酔い運転の方がはるかに重くなります。
4.酒酔い運転という判断は誰が下すのか
『この人の検挙理由は、酒気帯び運転ではなく、酒酔い運転』と誰がどうやって判断して決定するのでしょうか。
取り締まり時に現場にいる《警察官》が決められた検査をして判断し決定します。
- 歩行検査や警察官の質問に正常に答えられるかや、正常に会話をすることが出来るのかなどの検査が行われます。
飲酒運転で受ける処分は2つ!

飲酒運転で取り締まりを受けると、必ず2つの処分を両方受けることになります。
まず1つは、行政処分、そしてもう1つが刑事処分です。ここでは、行政処分と刑事処分について説明していきます。
1.行政処分とは
交通違反の行政処分を分かりやすくいうと、公安委員会が行う免許に対する処分のことです。
処分内容は主に、反則金や免許停止・免許取り消しなどになります。
この行政処分は、前歴にはなりますが、前科にはなりません。ただし、反則金を納付しなかったり、出頭通知を無視したりすると、刑事処分に変わり、処分が重くなります。
2.刑事処分とは
刑事処分とは、道路交通法に基づく刑罰のことです。
主に処分(刑罰)内容は、懲役刑・禁固刑・罰金刑になります。
この刑罰内容は、裁判によって決まり、行政処分とは違い前科になります。
◆飲酒運転の行政処分・刑事処分についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
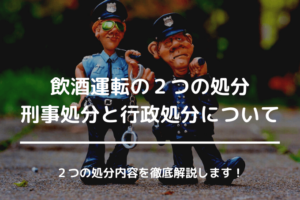
3.処分の流れ
飲酒運転で取り締まりを受けた場合の処分の流れについて解説します。
刑事・行政両処分2つの受けることになるということは上記で解説しましたが、順番的にいうと、まず刑事処分を受け、その後、行政処分を受けることになります。
まとめ

今回は、重大交通違反《飲酒運転》についての記事を書かせていただきました。
運転というものを職にしていた私ですので、飲酒運転というものをどんな理由があっても許すことは出来ません。
当たり前のことですが、《飲んだら乗るな!乗るなら飲むな!》です。
このブログにサイトでは、飲酒運転ついての記事をいくつも公開していますので、合わせてお読みください。